はじめに
こんにちは。RIVERISTのBORAです。
川のシーバスは「水温」で動く。
たった1℃の違いが、魚の活性と釣果を大きく変えることがあります。
本記事では、私BORAが実際の釣行で体感した“水温とリバーシーバスの関係”を軸に、季節ごとの狙い方と攻略のコツをわかりやすく解説します。
シーバスが動く「適水温」とは?
シーバスは変温魚で、体温を水温に合わせて変化させる生き物。
おおよそ10〜25℃の範囲で行動し、16〜22℃が最も活性の高い“ゴールデンレンジ”です。
| 水温 | 状況 | 行動傾向 |
|---|---|---|
| 10℃以下 | 活性低下 | 橋脚下や深場に潜む |
| 12〜15℃ | 春先に回遊開始 | 小型ベイトを追い始める |
| 16〜22℃ | ベスト水温 | ボイル頻発・ベイト追尾活発 |
| 25℃以上 | 活性低下 | 流れ込み・日陰に避難 |
季節ごとの「水温×戦略」
春(3〜5月)|上昇水温に乗る
春のシーバスは“冬の眠り”から目覚めるタイミング。
12℃を超えるころからベイトが動き出し、流れのある下流〜河口部に群れが現れます。
夏(6〜8月)|高水温を避ける
夏は25℃を超えるとシーバスの動きが鈍くなります。
狙うなら朝マズメ・夕マズメの「気温・水温の下がる時間帯」。
僕はこの時期、支流の合流点や堰下の“冷たい層”を意識して探ります。
気温が35℃でも、水温が1〜2℃低いだけで明確に反応が出ることもあります。
秋(9〜11月)|水温20℃前後で最盛期
秋はまさに「水温ドンピシャ」な季節。
ベイトも豊富で、潮・風・水温が重なると一気に爆発します。
由良川で水温20℃ちょうどの夜、流心をサスケ95SS(ima)でゆっくりドリフトさせていたとき、
「ドンッ」と衝撃のバイト。
銀色の魚体が月明かりに光り、60アップのリバーシーバスが姿を現しました。
秋は、まさに“魚のスイッチが入る”水温帯を体感できる季節です。
冬(12〜2月)|低水温期は“越冬の釣り”
水温10℃を切ると、魚は流れの緩い深場や橋脚の影に身を潜めます。
僕は冬でも釣りをやめないタイプですが(笑)、この時期は「狙う場所を絞る」ことが最重要。
バイブレーションでボトムをゆっくり舐める釣りに切り替えましょう。
水温チェックのおすすめ方法
- タイドグラフBIや釣り気象アプリで河口の水温をチェック
- 携帯型水温計をタモの先につけて実測(BORAも実践)
- 釣行ノートに「気温・水温・釣果」をセットで記録
これらの記録を積み重ねると、翌年“同じ水温帯で釣れた日”に再現できるようになります。
参考:タイトグラフBIについて
BORAの体験談|「水温1℃の差で釣果が変わる」
ある秋の夕方、由良川支流の温排水エリアをチェックしていたときのこと。
本流は水温18℃、支流は19℃。
たった1℃の差なのに、支流側ではベイトが表層を逃げ回り、30分で3本キャッチ。
一方、本流側は完全ノーバイト。
そのとき痛感しました。
“シーバスは流れを読む魚”であると同時に、“温度を選ぶ魚”でもある。
それ以来、僕の釣行前ルーティンは「潮汐・風向き・水温」の三点チェックが定番になりました。
RIVERISTまとめ
水温は“魚の時計”であり、“釣り人の地図”です。
水温を読むということは、自然のリズムを感じること。
単なるデータではなく、
「今日はこの温度、この流れ、この季節だから――この一尾に出会えた」と思える瞬間が、リバーシーバスの醍醐味ではないでしょうか。
RIVERISTでは、そんな自然との対話を大切にした“川の釣り”を伝えていきたいと思います。
あなたも、ぜひ自分のフィールドで“温度を読む釣り”を体験してみてください。
📩 あなたの「水温と釣果の記録」募集中!
「この水温で釣れた!」というデータや体験談をぜひRIVERISTで共有してください。
あなたの1尾が、全国のリバーアングラーのヒントになります。
👉 体験談募集ページはこちら

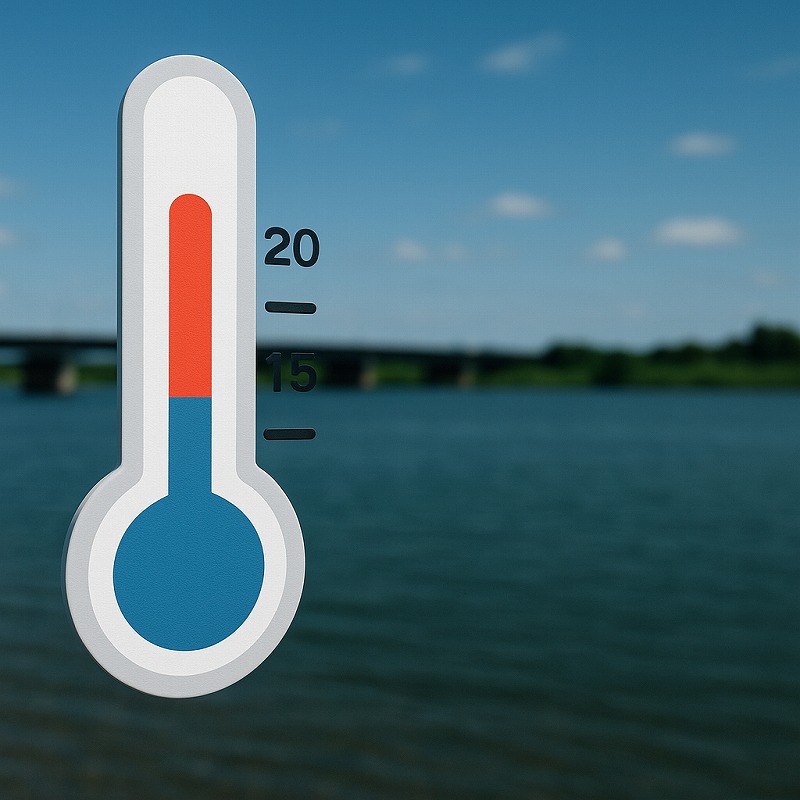
最近のコメント